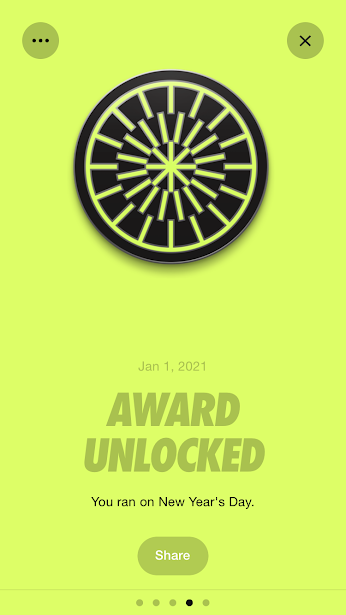製品ライフサイクル
導入期
導入期は消費者向けSP(セールス・プロモーション)だけでなく、流通業者向けSPによって製品の取り扱いを確保することも重要である。メーカーはまず小売店の棚に自社の製品を並べてもらうことが必要で、それはどれだけ消費者向けにセールス・プロモーションを行ったとしても、流通業者がその製品を取り扱わなければ、消費者の手元に製品は届かないためである。
情報提供型広告
「情報提供型広告」は、どのような製品かを知ってもらうための広告であり、導入期に適している。
リーチ
導入期には、まず多くの人に自社製品を認知してもらうことが重要になる。特定の広告がある期間内にどれだけ多くの人に閲覧されたかを示す値を「リーチ」という。つまり、多くの人に製品を認知してもらうことが目標の導入期には、リーチの方が重要になると考えられる。
成長期
成長期のテーマは、①ブランドの育成、②市場シェア拡大、③継続購買の促進である。
説得型広告
「説得型広告」は成長期に重要な広告タイプである。「説得型広告」では、 成長期に競合製品も販売される状況下において、なぜこの製品が優れているのかを訴求する。消費者を説得することで、ブランド選好(ロイヤルティ確立)を図るので ある。
成熟期
成熟期には市場シェアを維持することが必要である。そのために顧客の維持や購買頻度向上が重要になる。
リマインダー型広告
成熟期の広告タイプとしては、その製品のことを忘れないようにすることを目的とした「リマインダー型広告」が重要である。例えば、テレビではおなじみの製品がCMで繰り返し流されていることを想起するとわかりやすい。
フリークエンシー
「フリークエンシー」とは、特定の広告が特定の人にどれだけ閲覧されたかを示す値である。
衰退期
衰退期にある市場の顧客は一般的にロイヤルティが高いため、企業は当該事業を維持し続けることで、売り上げは小さくとも高い利益率を実現できる可能性は残されている。
計画的陳腐化
計画的陳腐化とは、製品ライフサイクルを意図的に短命化させることである。その目的は、消費者に新たな購買需要を喚起し製品の買い替えを促すことである。外観だけを変えることによって心理面で新製品であることを訴えることがある。例えば自動車のモデルチェンジの事例をあげることができる。技術革新のスピードが遅い製品領域で利用される。技術革新の遅い製品領域では、新たな購買需要が生まれにくい。そのため製品ライフサイクルを意図的に短命化することは、購買需要を喚起するきっかけとなり得る。本質的ではない部分の機能を変えることで、旧製品を古いと思わせることができる。例えば、携帯電話のディスプレイである。電話をかけるという本質的な機能は同じであっても、 ディスプレイをモノクロからカラーに変えることで、従来のモノクロ製品を古いと思わせることができる。